人混みに紛れ、音が氾濫し、慌ただしく過ぎていく日常。定年退職後、毎週のようにキャンピングカーで車中泊くるま旅に出かけ、日常から離れて、心と体の解放を求めた。一方で、雨の日や出かけずにおうちで寛ぐ休日もあった。
日曜日の朝、定時の4時30分を4時間も過ぎてゆっくりと目覚めた。椅子を取り出して、風で揺れる庭を眺めた。戯れるモンシロチョウのつがい、最近良く訪れてくれる小鳥の鳴き声、梅雨の時期に咲く花々など。1時間近くもまったりと過ごした。出かける週末とおうちにいる週末の対比。心が何故落ち着くのだろうと考えたら、「五感」が研ぎ澄まされるから。登山では、いつも体験しているあの感覚に近い。
今回の記事は、おうち時間が長くなる完全リタイヤ後に思いを寄せ、五感を意識的に使っておうちの休日時間を楽しむ方法について考えた。
土日にふと五感について考えた
今週末は、近くに住む子供たち夫婦と入れ替わり過ごすことになった。遅起きできる朝(冷感接触の掛毛布の触覚)は、至福であり、時間に追われることはない。土曜日は、ここ2ケ月ほど週末の定番となっているたまごサンド(味覚)を作って食べ、お庭の草むしりや咲き終わった花木の剪定(視覚、触覚、嗅覚)をしたり、その後、義娘とワンコと、お喋り(聴覚)しながらアフタヌーンティーもどきを楽しんだ。

日曜日も8時過ぎに目覚め、折りたたみ椅子を取り出して、しばらく庭を眺めた(視覚)。生暖かい風(触覚)、小鳥のさえずり(聴覚)、芝生の足感覚(触覚)など。午後から、娘夫婦の家にお邪魔し、孫のお守りをした。今は笑い声よりも泣き声(聴覚)が大きい。
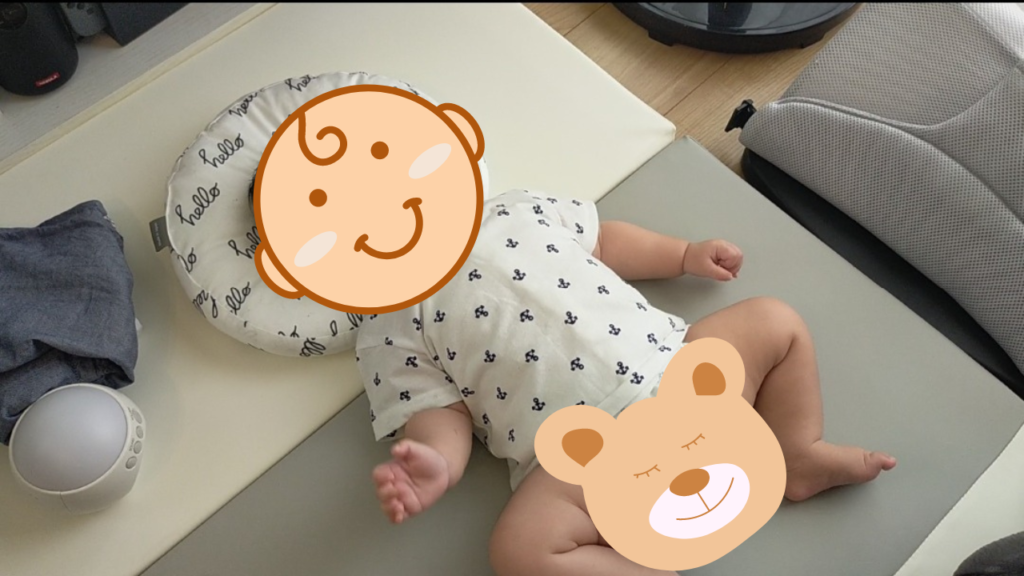
五感を刺激するおうち時間とは?
情報過多で疲れた脳を休ませるには、意識的に入力を選択する必要がある。自然豊かな場所に行くことも良いが、おうちで好きなものに囲まれて過ごすことが一番の特効薬だ。ゆっくりとした時間で、普段気づかないことを察知することができる。五感を意識することで、自分の周りの世界にも敏感になり、表現力が豊かになるように思う。
思いつくことを並べてみたら、、、
【視覚】
◯空を見上げる(観天望気、雲の変化)
◯映画鑑賞、絵画鑑賞
【聴覚】
◯鳥や虫の声
◯赤ちゃんの笑い声
◯まな板で野菜を切る音など
◯好きな音楽を聴く(昔のように、クラシックを1日中)
◯ウクレレやサックスを演奏する
【味覚】
◯旬の味覚を舌で季節を感じる
◯美味しいものを食べる
◯好きなものを作って食べる
【嗅覚】
◯好きな香りを楽しむ(アロマテラピー)
◯台所から漂ってくる匂い
【触覚】
◯指先や肌で風を感じる
◯愛する人に触れる
◯窓から入ってくるそよ風と光
◯DIY
嗅覚とは?
香りから過去の記憶を思い出す理由
そもそもどうして香りから、過去を思い出すのでしょうか。それは、人間の嗅覚と脳に深い関係があるからだと考えられています。脳は人間の思考を司る「大脳新皮質」と、感情を司る「大脳辺緑系」の2つがあります。人間の五感のうち、視覚や触覚・聴覚・味覚などは大脳新皮質を経由して、記憶に関係する「海馬」に届きます。ただ嗅覚のみ経由せず、海馬にも届きません。そのまま視床下部に送られることもあり、より記憶に強く印象が残ると言われているのです。
11201
もともと人間は、五感のなかでも嗅覚が最も早く習得するものであり、生命の維持のために必要なものであると考えられています。生まれたての赤ちゃんが母親を認識するのも嗅覚が働いているためです。また食べて良いもの・食べないほうが良いものを判断するときにも臭いを使うことがあります。嗅覚は重要な役割を担っているものでもあるのです。
情報判断をする五感の中で「嗅覚」が占める割合は2%と言われています。五感の中で情報判断をする割合が少ない「嗅覚」ですが、人の記憶に最後まで残るものは「嗅覚」なんです。「嗅覚」以外の五感と「嗅覚」では、脳への情報の運ばれ方が違うのです。人間の感覚の中で理性ではコントロールできない感覚なのです。大切な人の記憶に残り続けるには匂いがとても大切なのです。
人の生命が終わる時、最後まで残る感覚は「聴覚」です。ただ、記憶から最初になくなるのも「聴覚」です。これが深いですね!
香りを形にする物語
味覚とは?
「心が素直で、頭が洗脳されていなければ」というのは、味覚が余りにも敏感で、ちょっとしたものに影響されるからです。たとえば、カゼをひいて鼻が詰まっていると味が分からなくなりますが、これは五感の順序が「触覚─臭覚─視覚─聴覚─味覚」の順番になっていて、臭覚が閉じると味覚もダメになるからです。また飛行機のお弁当が不味いのも、ジェットの音が原因です。つまり味覚は信用できるのですが、敏感なので注意が必要ということがわかります。料理屋に行って食べる時より家のお母さんの料理がそこまで美味しく感じない原因は、食材や料理の腕もありますが、多くは「家の食卓が雑然として、テレビがついているから」とも言われます。 心を落ち着かせて、静かでゆったりしたところで、少しお腹がすいた時に自分が美味しいと感じるものを食べ、あまり極端にならない・・・健康とはそれに尽きるのでしょう。
武田邦彦メルマガ
老年期の感覚機能の低下――日常生活への影響
視覚と聴覚の衰えは、65歳前から自覚がある。
「嗅覚」一般に嗅覚は50歳代から低下が始まり,70歳代で急速に悪化する。嗅覚障害をきたす原因は50歳代以下では鼻副鼻腔疾患が多いが,60歳代以上では感冒罹感後や原因不明例が増加する。浅賀(1994)は,嗅覚障害をもたない場合,年齢増加に伴う老化現象としての嗅覚減退の程度は個人差が大きいものの50歳代から急激に進行することを示している。
「味覚」加齢に伴う味覚機能低下は視覚,聴覚,嗅覚に比べ相対的に衰えにくく脳障害等による味覚不全症を除けば食生活が困難になるほど味覚が衰えることはないと考えられる。しかし加齢や薬物の常用等に伴い,味覚受容の担い手である味蕾の数が減少しやすいこと,義歯や入れ歯等咀嚼能力の低下,味覚刺激で分泌される唾液量の減少や唾液中に含まれるアミラーゼ等の酸素活性の低下による消化機能の低下に個人差はあるが生じる。したがって高齢者では,食品中の呈味物質が唾液中に溶解する量は相対的に低下するので,同じものを食べても味覚強度が低下し,味覚情報による食物認知および嚥下において健常成人に比べより多くの時間を必要とするようになる。甘味については閾値・知覚強度とともに高齢者も若年者も安定に変わらないこと,塩味については少なくとも閾値レベルで感受性が低下することがほぼ一致した結論といえる。また,性差については男性の方が女性に比べて知覚感受性が衰えやすいこと,とくに苦味と酸味でその傾向が見られやすいこと,喫煙の影響は苦味の閾値に影響することなどが報告されているが,統一的な見解には至っていないようである。
「皮膚感覚(触覚)」高齢者の体温調節機能は,とくに65歳を超えたころから温度感覚の麻痺は顕著になる。老化により温度受容の機能の低下がみられ,感度が鈍くなることが分かっている。たとえば,入浴時に火傷をするのはこのためである。50歳以下では約0.5度の温度差の弁別ができるのに対し,65歳以上の高齢者では,約1.0~5.0度の温度差となって初めて弁別できるとされている。また,寒冷環境下では寒さに対応する「震え」の生理的な防御反応の出現が遅れるため,体内温の低下が大きく,暑熱環境下では発汗量は少なく体内温の上昇が大きいことが判明している。次に,体温調節で発汗のメカニズムが重長となってくる。発汗には,一般の温刺激による温熱性発汗,そして冷汗が出るという精神性発汗,わさびや唐辛子などの刺激物を摂取したことによって顔などに出る味覚性発汗がある。温熱性発汗は手掌,足底をのぞく全身でみられ,ここではエクリン腺(小汗腺)が関与する。汗腺数は,老化により減少は認められていないが,汗腺あたりの発汗数は低下することが分かっている。このことは老化に伴う発汗の抑制に,汗腺の機能低下という末梢要因が関与していることを示している。70歳以上の高齢者は若年者に比べると,皮膚の各部位とも,発汗の始まる体内温度が高くなることが分かった。このように高齢者では温熱刺激に対する発汗の応答が抑制されているため水分の蒸発により熱放射の量が高齢者では少ないために温環境下で体内温度が上昇しやすくなることが分かっている。触覚・圧覚は老化により鈍くなる。また老化により触点が減少し,触覚小体の数も減少することが分かっている。
「聴覚」加齢により最小可聴限が上昇し,可聴周波数範囲が狭くなることはよく知られている。空気の振動が音として聞こえる範囲が可聴範囲であるが,可聴範囲には周波数による可聴周波数範囲と音圧で測定される最小可聴閾・最大可聴閾がある。可聴閾として問題になるのは,最大可聴限よりむしろ最小可聴限の方である。加齢に伴って可聴周波数範囲では高い音が聞きにくくなり,最小可聴閾値が高くなるため小さな音が聞こえにくくなるなど可聴範囲が狭くなる。さらに,音の大きさの弁別や高さの弁別が困難となり,両耳効果の低下とマスキング効果の増大などのため可聴閾値が増大する。
「視覚」視力は比較的若い時期から加齢とともに低下し,高齢者の裸眼視力は,生理的な角膜と水晶体の屈折力の変化と網膜黄斑部の変化,視細胞の感覚能力の減退などにより低下するが,さらに,白内障,黄斑部変性,網膜血管硬化症などの眼の病気により低下する(中村,1957)加齢に伴って暗順応,明順応ともに長時間を必要とするようになる。順応による視感度測定は,刺激閾または弁別閾によってなされるが,加齢の影響は明順応より暗順応の方が顕著である。視野は加齢に伴い網膜の感受性の低下,水晶体の障害,眼調節力の低下などにより狭くなる(Wolf,1967)。また,脳萎縮感覚機能の低下,脳動脈硬化などによる脳に器質的な変化が生じると,視野狭窄,視覚失認などが起こることがある。視野の外側,内側,下側とも年齢と共に見える範囲が狭くなっていくが,とくに上側は見える範囲が狭くなるために前方上方視が困難になることが指摘されている。
駒澤大学心理学論集(KARP),No.6,2004
意識的にメリハリをつける
今はまだフルタイムで働き、週末に寛ぐ生活があるので、緩急のメリハリがある。完全リタイヤになると、「緩」だけの生活になりがちなので、意識的に「急」を見つける必要がある。
参考
五感という言葉をググってみたら、面白いことをたくさん見つけた。結構あったので、一部だけ記憶にとどめたい。
キナリノ
五感を刺激して子育て


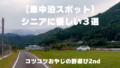
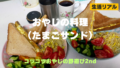
コメント